SaaS(ソフトウェア・アズ・ア・サービス)やサブスクリプションモデルを採用するスタートアップにおいて、新規顧客を獲得することは重要ですが、それ以上に「獲得した顧客がどれだけ長く使い続けてくれるか」が企業の収益・成長に直結します。LTV(顧客生涯価値)を最大化するためには、オンボーディングとその後のカスタマーサクセス/サポートが肝となります。
本記事では、実務担当者(マーケ/CS/営業)がすぐ使える具体的な施策を中心に、SaaS オンボーディングのベストプラクティス、チャーン率(解約率)低減の方法、LTV の高め方を解説します。
SaaSにおけるオンボーディングと継続率の関係

SaaS オンボーディングとは、ユーザーが登録してから初期設定を行い、プロダクトの主要機能を使い始めて「最初の価値(First Value)」を実感するまでの一連の体験設計を指します。良質なオンボーディングがあると、ユーザーが途中で離れてしまう率を下げることができ、継続率が向上します。複数のレポートにおいて、First Value が早く感じられるよう導くことが継続率に強く影響するという結果が示されています。
最近のデータでは、B2B SaaS の月次チャーン率の平均が約 3.5% 程度であることがわかっております(Voluntary チャーンが約 2.6%、Involuntary チャーンが約 0.8%)。また、Net Revenue Retention(NRR:既存顧客からの収益をどれだけ維持・拡大できているかを示す指標)の中央値は約 106% であり、上位企業では 120% を超える例もございます。Gross Revenue Retention(GRR:拡張収益を含まない離脱のみを除いた収益維持率)については、多くの SaaS 企業で 90%前後、優良企業では 95%以上 を達成しているところも報告されております。
これらの数値は、オンボーディングや継続サポートの強化が、どれほど実際の継続率/収益維持に関係するかを示しており、実務担当者が目指すべき水準の参考になります。
SaaS オンボーディングのベストプラクティス
まず登録や導入初期の体験を簡素化することが肝要です。サインアップ時の入力項目をできる限り削減し、必要でない情報や複雑な設定は後回しにすることで、ユーザーの負荷を減らせます。さらに、ユーザーの役割や用途、契約形態などでセグメントを分け、その属性に応じた導線を設計することで、使い始める動機や目的に合った導入が可能となります。
続いて、First Value を実感してもらうまでの時間を可能な限り短くすることが重要です。オンボーディングウィザードやプロダクトツアーを活用し、チェックリストや進捗バーを設けて、どのステップが残っているかをユーザーに可視化すると、迷いを減らしやすくなります。初期の成功体験、たとえば初めてのレポート生成や設定完了など、ユーザーに成果を感じさせる体験を意図的に設計することで、「このツールを使ってよかった」という感覚を早く持ってもらえます。
教育支援とフォローアップ体制も整えるべきです。ナレッジベース、動画チュートリアル、FAQ などのセルフサービス資料を充実させるとともに、登録後未ログイン・主要機能未使用などのユーザーに対してトリガー通知やリマインダーを送ることで、離脱の手前で介入できます。さらに、ウェビナーやライブデモを定期的に提供してユーザーの疑問を解消し、操作方法や活用方法のヒントを直接伝えることが、信頼感の醸成にもつながります。
オンボーディングの改善は一回限りではなく、継続的に行う必要がございます。Time to First Value(First Value を実感するまでの時間)、アクティベーション率、ログイン頻度、主要機能の利用率といった指標を設定し、データ分析を通じてどのステップでユーザーが離脱しているかを把握することが大切です。加えて、ユーザーからのフィードバック(アンケート・NPS・CSAT 等)を取得し、どこに不満や改善の余地があるかを明らかにして、施策に反映させ続けることがオンボーディング質改善の鍵となっています。
継続率を高めるカスタマーサクセス/サポート戦略

オンボーディングが終わった後も、ユーザーがサービスを使い続けたくなるような環境を整えることが、継続率と LTV の向上には欠かせません。まず、顧客健康度スコア(Customer Health Score)を定義し、利用頻度・ログイン間隔・主要機能の使用状況・問い合わせ履歴など複数の指標を取り入れて、離脱リスクがある顧客を早期に検知できる仕組みを構築することが重要です。
さらに、お客様を契約規模・ARPU・利用用途などでセグメント分けし、ハイバリュー顧客には対面や手厚いハイタッチ CS を提供し、対して小規模の顧客や標準プランの顧客にはセルフサービスや自動化されたサポートを中心にするロータッチ方式を組み込むことで、コストを抑えつつ継続率を高めることができます。
また、定期的なチェックインを行うことが効果的です。オンボーディング完了後、数週間後や1ヶ月後など、利用状況を確認し、予想された利用がされていない機能があればヒントを提供したり、ヘルプを案内したりすることが望ましいです。さらに、プロアクティブなサポートとして、利用ログから異常を検知した際にはこちらからコンタクトを取ること、さらなる活用やアップセルの提案を行うことが、ユーザーとの関係を強化し、継続を促します。
契約や価格体系に柔軟性を持たせることもまた重要です。顧客の成長フェーズや利用スタイルに応じてプランを変更できるようにし、アップグレード・ダウングレード・一時停止などの選択肢を用意しておくことで、契約を解除されるリスクを減らすことが可能になります。
最新データから見るチャーン率低減と LTV 向上の目安
2025年の業界ベンチマークによりますと、B2B SaaS の月次チャーン率平均は約 3.5% で、そのうち自主的解約(voluntary churn)が約 2.6%、支払いや請求関連の非自主的な離脱(involuntary churn)が約 0.8%という内訳でございます。また、Net Revenue Retention(NRR)の中央値はおおむね 106% 前後であり、最も優れた企業では 120% を超える例も確認されております。Gross Revenue Retention(GRR)については、多くの企業で約 90% 程度、トップクォータイルでは 95%以上 を維持しているところもあります。
これらの数値は、オンボーディングやカスタマーサクセス体制を強化することで、継続率や顧客価値(LTV)をどれだけ改善できるかの目安として実務で使いやすい指標です。
実例
SaaS・自治体・教育・製造業といった、導入ハードルが高く、継続率が課題になりやすい領域で効果検証を実施しました。
① 自治体DX:人事異動リスクを超える仕組み化
自治体では、導入初期にシステムを理解していた担当者が異動してしまうケースが多く、
「導入したけど使われていない」という課題が頻発していました。
“引き継ぎ前提のオンボーディング” を設計。
- 導入時に庁内共有マニュアルと操作動画を自動生成
- 稼働率低下を自動検知してリマインド通知
- 定期的なフォローコールで、未稼働自治体を再稼働
結果、導入初期の稼働継続率は業界平均60%台 → 約88% まで改善(目安値)
自治体側からも「導入後の定着支援」を評価いただく
② 教育SaaS:教職員の“最初の壁”を越える設計
学校や学習塾では、ITリテラシー差や多忙さから、導入初期に利用が止まるケースが多く見られます。
教育委員会や学校現場と連携し、利用者属性別のオンボーディングを構築
- 管理者向けに「導入ガイド+校内説明用動画」を提供
- 教員向けには「授業準備中にすぐ使える5分チュートリアル」
- 未ログイン者にはLINE連携で自動フォロー
この結果、初期アクティベーション率は 約90% に到達(業界平均:60〜70%)。
3ヶ月後の継続率(GRR)も 95%前後 を維持
③ 製造業SaaS:現場起点の“成功体験”設計
AI画像認識や設備点検など、製造業向けSaaSでは「現場が使いこなせない」ことが課題。
営業部門とCS部門を横断して、現場伴走型オンボーディングを実施しました。
- 導入初週で「初回設定→初回点検完了」まで伴走
- コール+リモート支援のハイブリッド対応
- 利用ログをもとに活用レポートを定例共有
結果、First Value 到達までの平均期間は 9.2日 → 3〜5日 に短縮(目安値)
初月継続率も 90%台前半 を安定的に維持
現場で見えてきた3つの成功パターン
現場での支援を通じて見えてきた、オンボーディング成功の共通点は以下の3つです。
1️⃣ 初期摩擦を徹底的に減らす設計
→ サインアップ、設定、初回操作など“最初の壁”をすべて簡略化する
2️⃣ First Valueを最短で届ける伴走型支援
→ 「できた」「使えた」という体験を初期段階で必ず届ける
3️⃣ プロアクティブなフォロー体制
→ 離脱リスクのあるユーザーをデータで検知し、事前に支援する。
この3つを仕組みとして設計することで、平均GRR 94〜96%/NRR 110%前後 を安定的に維持する企業群が生まれています。
まとめ
SaaS スタートアップにおいては、顧客を獲得するだけでなく、その顧客に使い続けてもらうこと、つまり継続率を上げることが収益の安定と成長の要です。2025年時点の業界データからは、月次チャーン率が約 3.5%、NRR が約 106%、GRR が約 90%前後という数値が示されており、これらを目標としてオンボーディングとカスタマーサクセスの改善を行うことが現実的で意味があります。
オンボーディングでは、登録初期の摩擦を減らし、First Value をできるだけ早く体験させる導線を設計することが肝要です。教育支援・フォローアップを整備して、ユーザーが迷ったり戸惑ったりしないよう支えることも重要です。カスタマーサクセス/サポートにおいては、顧客健康度の見える化、セグメントごとの対応、プロアクティブなフォロー、契約・価格の柔軟性を持たせることが継続率向上に直結します。そしてこれらの施策を実践する際には、指標をきちんと追いながら改善サイクルを回すことが、LTV を最大化する道となります。

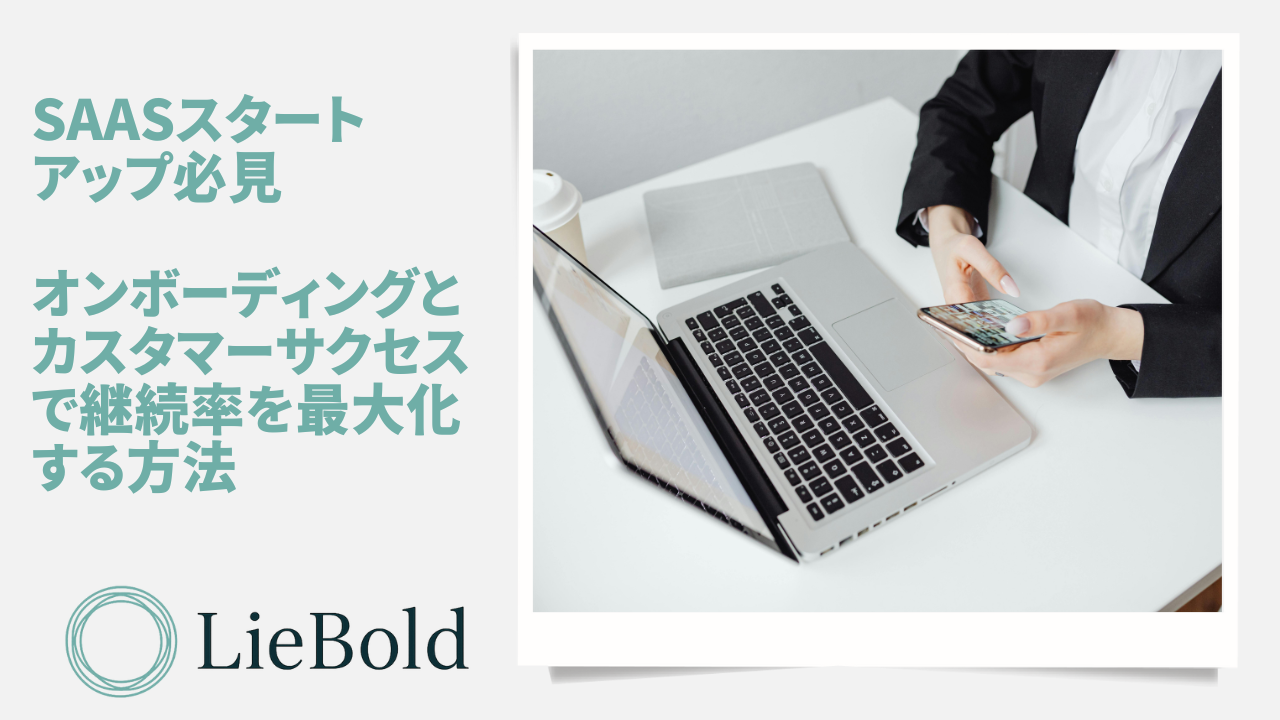



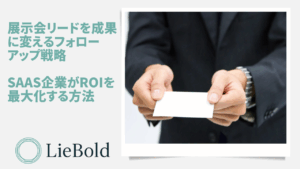




コメント